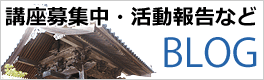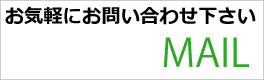チャレンジスクール餅つき大会!①
2026-01-09
12月21日(日)
チャレンジスクール、12月の講座は「餅つき大会」を行いました。
朝早くから食推の方は来られて準備を始めていました

もろぶたを出してきたり作業はたくさんありました

チャレスクの子どもたちは待ち遠しそうに待っていました

さあもち米が蒸しあがり、餅つきが始まりました

よいしょ! と毎回掛け声がとんでいました





丸める作業が楽しいようでみんなで奪い合うようにしていましたので、あっという間に終わりました。
メロンパンを作りました!
2025-12-24
11月19日(水)

今回は早く始められるようにあらかじめ1次発酵まで終わった状態のものを持って来ていただきました。

こねてこねて成型を行いました!

1回目を焼いている間に持ち帰り用の粉を練る作業もしっかりと行いました。

途中経過の写真がなくもう焼きがり!? と思うかもしれませんが、どの写真も同じようにしか見えないためです……。

とっても美味しいそうなメロンパンが出来上がりました。
桂林ウォーキング大会(後半の部)
2025-12-22
11月16日(日)
桂林ウォーキング大会 Vol.2、後半部分をお届けします。

いいちこ日田蒸留所のある高台を目指してこれから登ります。

高台に到着!(撮影班は道路事情の都合で遠回りしたためどの程度の坂道だったかは……。





いいちこ日田蒸留所に到着です。

大人の人たちは到着後解散のためめいめいで屋台料理を楽しんでいました!

いいちこの森の中には楽しそうなハンモックなどもありました。
桂林ウォーキング大会
2025-12-20
R7.11.16 Sun
桂林ウォーキング大会(桂林体協主催)が16日(日)に行われました。桂林公民館からは、ぶらり歩こう会とチャレンジスクールで出場しました。
秋晴の中、紅葉祭が行われているいいちこ日田蒸留所を目指して約4㌔のウォーキングを楽しみました。





出発前に記念撮影! たくさん方に参加いただきました。






休憩ポイントでは空くじなしの抽選会が行われ、紅葉祭で食べられる“豚しゃぶ券”などが当たり、参加したチャレスクの児童たちは大喜びしていました。
公民館だよりR7.12月1日号を発行しました
2025-12-10
公民館だより「第171号」を発行しました。今号は“子育てサロンの募集について他、各事業の報告”などを掲載しています。
 広報 令和7年12月1日号 |
海辺の道をぶらりと歩く
2025-12-03
10月29日(水)
ぶらり歩こう会、年1度の市外研修を開催いたしました。今年は福岡県岡垣町の遠賀宗像自転車道(サイクリングロード)にて開催しました。同道は宗像市から芦屋町まで続く歩行者や自転車の専用道路のため、安全に通行できる上、ほぼ全線が海岸線に沿って作られているため景観の良い場所となっていました。遠くには薄っすらと世界遺産「神宿る島・沖ノ島」を眺めることができました。








第10回桂林ふれあい祭 Part 7
2025-11-21
10月19日(日)
ふれあい祭 Part 7は、祭りにいろどりを添えた飲食店などの紹介です。
おなじみの城新ボーイズの皆さんによる「焼きそば」です。お昼近くになると行列のできる焼きそば屋台となるため早くから準備をしていました。


桂林地区壮年会の皆さんが、鳥炭火焼を焼いているところです。こちらも大変人気のあるお店となっています。


どのお店も完売となる賑わいでした。ご来場いただきありがとうございました。
第10回桂林ふれあい祭 Part 6
2025-11-18
10月19日(日)
第10回桂林ふれあい祭編、続いては室内展示などについてご紹介いたします。








第10回桂林ふれあい祭 Part 5
2025-11-17
10月19日(日)
ふれあい祭Part5は、最後の演目「梅后流江戸芸かっぽれ教室」の皆さんです。



演目は終わり、残りはみんな楽しみな抽選会です。

抽選会が始まるとあって多くの人が集まって来られました!

見事、抽選会で当たった方は満面の笑みで喜ばれておられました。
第10回桂林ふれあい祭 Part 4
2025-11-14
10/19(日)
第10回桂林ふれあい祭報告Part4。今回は、空手に続いて剣道の練習披露の模様をお伝えいたします。

一列に並んで礼!

最初は素振りの練習から、今年入ったばかりでまだ防具も着けないちちゃな子どもががんばって竹刀を振っていました(振り回されていたかな?)

続いてはぶつかり稽古。先輩剣士にメーン!


ぶつかり稽古。チビッ子剣士の次は大人の稽古の様子でした。子どもとは違い激しいぶつかり合いを披露していました


最後は、また全員で一礼して終わり。 « Older Entries